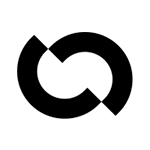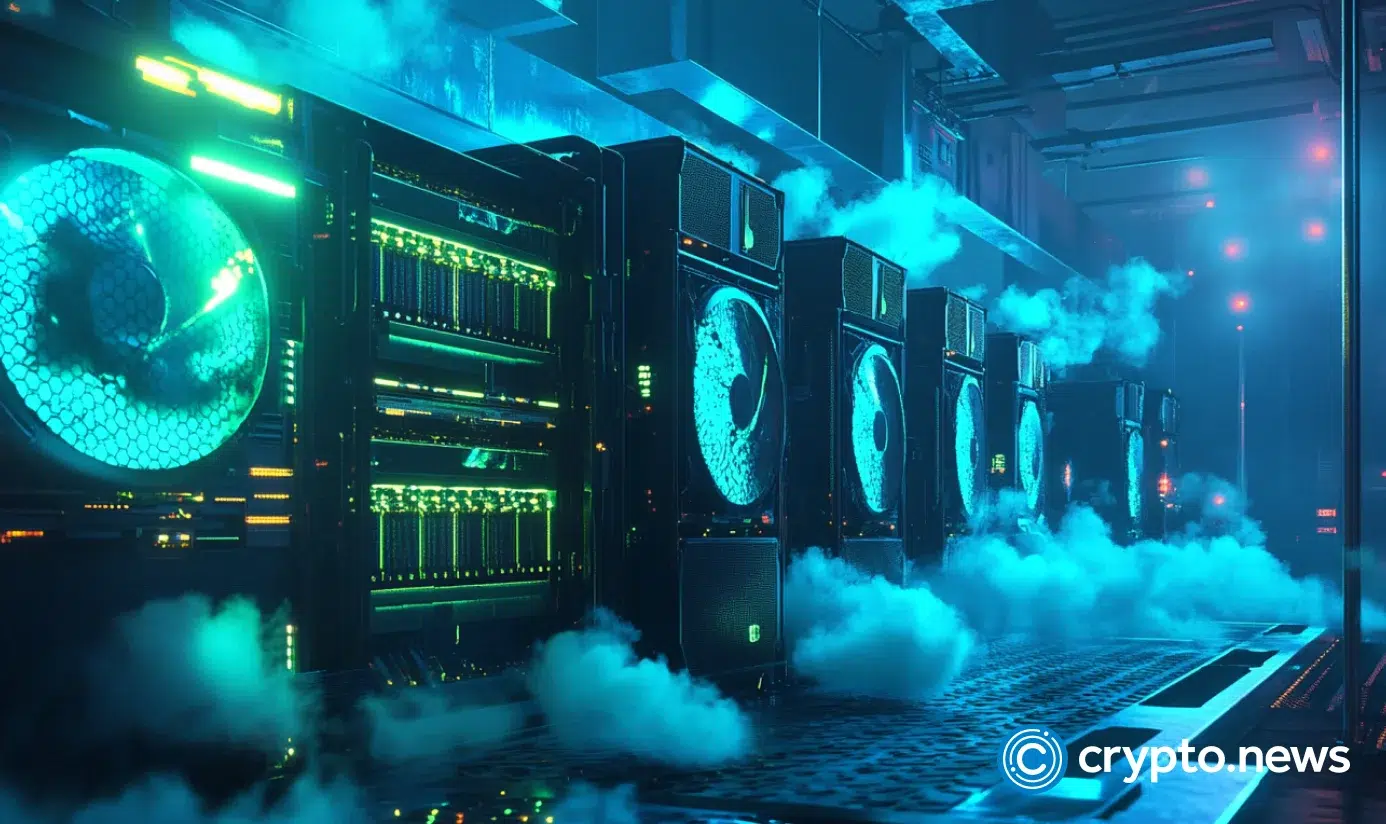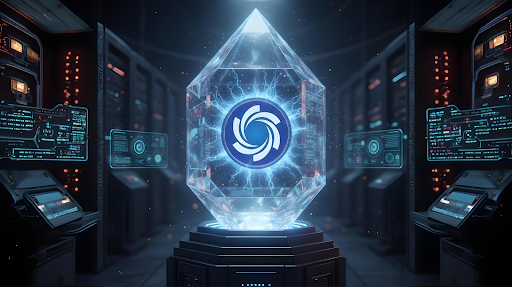アジア発!ステーブルコイン最前線を解説

アジアのステーブルコイン競争、各国の動きと今後の展望
ここ最近、アジア各国でステーブルコイン(価格が安定した仮想通貨)をめぐる動きが活発になっています。特に日本、シンガポール、香港などが新しいルール作りや実証実験を進めていて、今後の仮想通貨と金融政策の関係がどうなるのか注目されています。
政府と民間のバランスを探る動き
アジアの各国政府は、金融の近代化と自国通貨のコントロールのバランスをどう取るかを模索しているようです。民間のステーブルコインがどこまで国の金融システムに組み込まれるのか、実際にテストが始まっている段階だと伝えられています。
日本・シンガポール・香港の最新動向
- 日本:三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが、来年3月までに円建てのステーブルコインを共同発行する計画を進めているそうです。これに合わせて、仮想通貨のインサイダー取引禁止など、デジタル資産に関する規制も強化される見込みです。
- シンガポール:StraitsXという企業が、シンガポール・ドルに連動したXSGDトークンを発行し、中央銀行の監督下で運用しています。最近ではCoinbaseにも上場し、国際的な注目も集まっています。
- 香港:大手テック企業が香港でのステーブルコイン事業を進めようとしたものの、中国本土からの指示で計画がストップしたという話も出ています。規制の壁が見えてきた形です。
各国のアプローチの違い
アジアでは、銀行が主導する国内通貨型のステーブルコイン、規制はあるけどイノベーションを重視するモデル、そしてコンプライアンス(法令順守)を最優先する保守的なモデルなど、いくつかの方向性が出てきているようです。
例えば、日本は銀行連合による安定した運用を目指していて、シンガポールはグローバルなイノベーション拠点としての役割を強めています。香港は、企業向けの用途や規制重視の姿勢が目立つとの見方もあるようです。
今後の展望と課題
こうした動きの背景には、国際的な金融インフラの標準化(ISO 20022など)も影響していると言われています。各国ごとに事情やアプローチは違いますが、技術面ではまだ発展途上な部分も多いようです。
アジアのステーブルコイン競争は、今後も各国の政策や民間企業の動きによって大きく変わっていく可能性がありそうです。どのモデルが主流になるのか、引き続き注目していきたいですね。